世界の学びを
文具の力で後押し!
キャンパスの未来

コクヨの挑戦「ヨコク」を描く社員たち。
今回はコクヨの文具を世界に広げる取り組みに挑む
メンバーのヨコク「文具で世界中の学ぶ意欲を
掻き立てます!?」に込めた想いに迫ります。
この記事は約8分で読めます
INDEX
Profile

本村 香代子(もとむら・かよこ)
グローバルステーショナリー事業本部 グローバルリージョン統括本部 マーケティング戦略推進本部

中内 和郎(なかうち・かずお)
グローバルステーショナリー事業本部 グローバルリージョン統括本部 グローバル営業第1部 第1グループ

Sze Jessica
グローバルステーショナリー事業本部 グローバルリージョン統括本部 グローバル営業第1部 第1グループ

齋場 麻実(さいば・まみ)
コクヨインターナショナル (マレーシア) Sdn.Bhd.出向
アジア市場のリアルに迫る
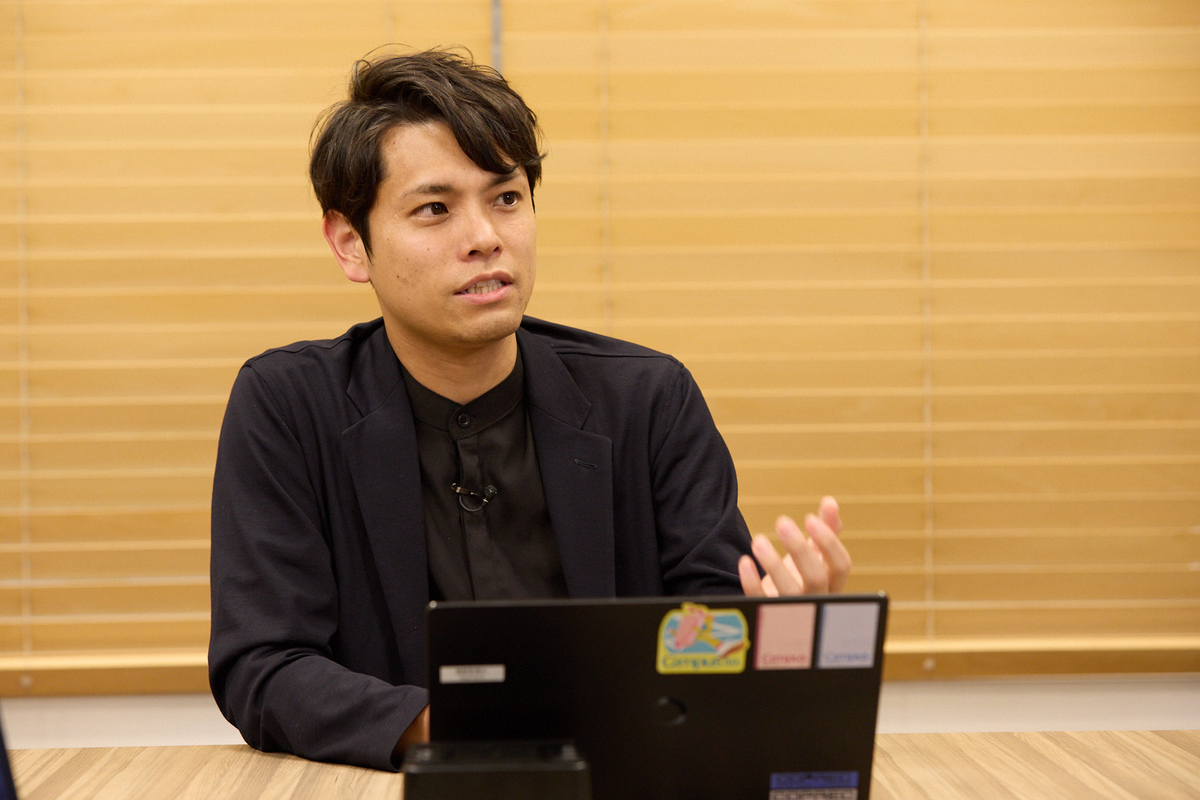
インタビューに答える中内
―まず、皆さんの担当領域とそれぞれの市場の特徴を教えてください。
中内:私はフィリピンとインドネシアを担当し、市場調査から戦略立案、マーケティング施策の実行まで幅広く手掛けています。両国では、まだコクヨ商品は十分に浸透しているとは言えません。日本発ならではの品質や機能性を強みに展開していますが、中国メーカーが急速に追い上げてきており、差別化は容易ではないのが現状です。

それぞれの担当エリアからリモートで取材に参加
齋場:私はマレーシアとシンガポールでの営業活動と、マレーシア直営店の運営を担当しています。コクヨ商品は現地メーカーに比べてデザイン性が高く、見た目でも目を引きやすいのが特徴です。さらに「使いやすさ」への工夫も強みです。ただし、価格はローカル商品より高めになることが多く、その分価値の伝え方に工夫が求められます。
ジェシカ:私はタイでの営業活動を担当しています。タイ市場におけるコクヨ商品の強みは「可愛らしさ」と「機能性」を兼ね備えつつ、価格も「中価格帯」に収まっているというバランスの良さにあると思います。

インタビューに答える本村
本村:私はマーケティング全般、とくにCampusブランドのグローバル戦略を担当しています。各国の学生が「どのように勉強しているか」「どこでつまずくのか」を理解したうえで、学びを支援するブランド体験をどう設計するかを考えています。商品・売り場・コミュニケーションを一体で構築し、各国の営業メンバーが動きやすい環境をつくっていくことが役割です。
“学び”を変える文具のチカラ
―各国での展開において「学び」を切り口にしているとのことですが、その背景を教えてください。
中内:私たちは現地市場に後発で参入しているため、価格に加えて知名度の面ではどうしても不利な立場にあります。だからこそ、コクヨの強みである幅広いラインナップを“学びの体験”と結びつけて提案することが重要だと考えました。フィリピンやインドネシアの教育は、日本と同じように”詰め込み型”から”主体性や創造性”が注目されつつあり、その兆しが見え始めています。このタイミングだからこそ、文具はその変化を支える一つの手段になれるはずです。ノート、筆記具、ファイルといった単品での機能訴求にとどまらず、「どう学び方を変えられるか」をセットで提案していくことで、学びそのものの変革に貢献していきたいと考えています。

グローバル展開している文具の一例
―では、「学び」にもっとも近いブランドであるために必要なことは何でしょうか?
齋場:まずは実際に使っていただけなければ何も始まりません。そのためには、手に取りやすい環境を整えることが重要だと考えます。直営店では、お客様がコクヨの商品に触れた瞬間の驚きや喜びを直接感じることができます。しかし一方で、一般的な文具店ではまだ取り扱いが少なく、マレーシアの方の日常に十分に根付いていない現実も痛感しています。学生たちが限られたお小遣いをやりくりしながら、ノート一冊を真剣に選ぶ姿を見ると、「もっと手に取りやすい価格で、もっと身近な存在になること」が必要だと強く感じています。
-

タイで初開催したPOP UP SHOPの様子(2023年)
-

東南アジア初の直営店をマレーシアに開店(2023年)
-

インド初のPOP UP SHOPのスタッフたち(2024年)
-

ベトナムで初開催したPOP UP SHOPの様子(2024年)
価格の壁を、どう超える?
―現地展開するうえでは、やはり「学生が手に取りやすい価格」がポイントになりますね。
ジェシカ:現在タイでは、バンコクやインターナショナルスクールなど比較的裕福な層を中心に利用していただいています。ただ、コクヨの商品をより広く浸透させ、日常的に使っていただくためには、価格がまだ大きな壁になっています。もっと多くの学生に届くよう、価格面での工夫が欠かせないと感じています。
―では、その課題を突破するために必要なことは何だと思われますか?
齋場:どうしても現地で手軽に買える文具と比べると、コクヨ商品は価格が高めです。もちろん機能性はありますが、「なぜこの商品は少し高いのか」「その価値はどこにあるのか」を伝えるのは簡単ではありません。さらに、日本では当たり前と思えることが現地では新鮮に受け取られる場合もあり、私と現地のチームメンバーとで「どこに価値を感じるか」が違うこともあります。だからこそ、マレーシアのお客様に実際に商品を使っていただき、その声をフィードバックとして取り入れています。そのうえで価値を整理し、丁寧に伝えていくことを大切にしています。
世界中で愛されるCampusブランドを目指して

―Campusブランドを世界に広めることで、どんな社会をつくっていきたいですか?
本村:Campusブランドは今年で50周年を迎えました。これからは単なる「ノートのブランド」ではなく、「学生の学び方を応援するブランド」へと進化させたいと考えています。マーケティングの立場から見て感じるのは、日本でも海外でも「どうやって勉強したらいいのか」と悩んでいる学生は多いということです。だからこそ、Campusを通じて一人ひとりが自分に合った学び方を見つけられる社会を実現していきたいです。その先には、自信を持って学びに取り組み、夢や目標に向かって前進できる未来があるはずです。進学や新しいチャンスにつながる可能性を広げるために、私たちは学生の挑戦を後押しする存在でありたいと思っています。
中内:私が目指すのは、AIや機械が進化していく時代でも、人間が人間らしく生きられる社会です。テクノロジーが進めば進むほど、私たちは創造性や主体性といった“人間ならではの力”を発揮しなければ、働くことも幸せに生きることも難しくなると思います。だからこそ、そうした力を引き出し、一人ひとりが自分らしく未来を切り拓ける社会をつくっていきたい。その実現に向けて、文具は大きな役割を果たせるツールだと考えています。
―Campusブランドを通して、世の中の人々のどんな「好奇心」を引き出したいですか?
ジェシカ:コクヨの文具を通して、学びの時間に「小さな発見」や「ちょっと試してみたい」という気持ちを生み出したいと思っています。例えば「このノートにはどんなペンが合うかな」「次は違う修正テープを使ってみよう」といったワクワクです。そうした小さな好奇心の積み重ねが、勉強そのものを前向きで楽しい時間へと変えていくと信じています。
本村:ある社員のエピソードをご紹介します。学生時代、勉強が苦手だった彼が「キャンパスノート ドット入り罫線」を使ったことでノートをきれいにまとめられるようになり、先生に褒められたそうです。その経験が自信となり、「もっと勉強してみよう」という意欲につながりました。そして大学に進学し、今ではコクヨの仲間として一緒に働いています。
このように、私たちの文具は学びを少し楽しくし、自分を信じるきっかけをつくることができます。だからこそ、世界中の学生に「やってみよう」と思える前向きな好奇心を届けられると思っています。
―最後に、今後挑戦したいことを教えてください!
齋場:まずは、現在運営している直営店をしっかりと軌道に乗せることです。日々多くの情報が集まってきますが、まだ十分に活用できていない部分もあります。そこを整理して成果につなげるとともに、マレーシアのステーショナリー事業をさらに盛り上げたいです。売上拡大はもちろん、メンバーが前向きに挑戦できるチームづくりにも力を入れていきたいと思います。
ジェシカ:今まさに挑戦しているのは、大手書店や文具店での売り場拡大です。現在はバンコク市内の大型店舗が中心ですが、郊外や小規模店舗にも展開していきたいと考えています。より多くのお客様にコクヨの文具を手に取っていただける環境をつくることが、今後の目標です。
中内:文具を販売すること自体は大切ですが、アジアの人口増加や教育環境の変化を踏まえると、「文具のあり方」そのものを問い直す必要があると思っています。とくに学びや教育は、これからさらに掘り下げるべき大きなテーマです。日本に限らず、グローバルで見て教育がどう変わっていくのかをしっかりと捉え、その中でコクヨが提供できる価値を明確にし、形にしていきたいと考えています。
本村:コクヨの文具にはお客様のことを考え抜いたこだわりが詰まっています。その価値を世界中に届けることで、学生たちの青春を応援したいと考えています。同時に、グローバルに挑戦する仲間たちがより活動しやすくなるようCampusというブランドをさらに強く育てていきたいです。そのために、生産から販売までバリューチェーンをしっかりとつなぎ合わせ、世界中で選ばれるブランドを築いていきたいです。
